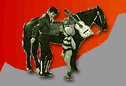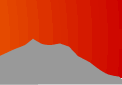|
昭和36年の夏頃、日活西部劇が全盛の頃(快調な「渡り鳥シリーズ」と宍戸錠さんの「早射ち野郎」に代表される和製ウェスタンなど)、一冊の本が出版されました。その名も「日活西部劇読本」です。
これぞ、ブームの極めつけであり証明です。アキラさんとジョーさんのガンプレイのグラビアを経た後の文章が凄いです。映画評論家先生方の絶賛の嵐。
ちなみに執筆されている先生は、双葉十三郎、南部僑一郎、佐藤忠男、品田雄吉(敬称略)の4人。
これをみると、後のあまり芳しくない評価とはうらはらのような気がします。全体を通じていえることは内容の評価云々ではなく、確実に時代が求めた結果として生まれてきた数々の作品が文化たりえていることを評価されています。以下に、それらの内容を要約したものを転載します(昭和36年当時)。
日活映画の魅力 双葉十三郎
誰に訊いても、日活映画は面白いという。少年はもちろん、分別くさい大人までも。それは観ると気持ちがすっきりするからである。日活にも芸術的価値の高い作品がないでもない。しかし、日活が今日の盛大を誇るのは、ダイヤモンド・ラインの諸君の活躍によるアクション・ドラマのおかげである。
活劇は、他社でも作っていたが、どうも理屈っぽく古くさい道徳的なワクにはめられている。日活のアクション・ドラマは大胆な構成と演出でスピードも快適で理屈ぬきに楽しめる。
この日活活劇の魅力を分析すると、一つは俳優の魅力である。それぞれ独自の個性を持つ諸君が揃っているので似たようなストーリーであっても、主演者によってまるで違った面白さが生み出される。それが大きな魅力である。
若い監督が揃っていることも魅力の一つである。活劇のよさは西部劇と同様、ファンの気分をスカッとさせるところにある。日活の活劇は、それをよくわきまえている。およそ活劇の筋書きは似たりよったりで馬鹿らしいものが多い。まじめにやればやるほどボロが出る。例えば小林旭の活劇からあの喜劇味をどけてしまった場合を想像してみられよ。宍戸錠の「ろくでなし稼業」だって、あのトボけたおかしみあればこその魅力である。赤木圭一郎の遺作「紅の拳銃」にしても拳銃教育場面のしゃれっ気があればこそ、現代の若いファンに歓迎されるのである。
それだけではない、活劇ではなんといっても射ち合いや格闘など、アクションが大切である。そのあたりは日活は手を変え品を変え、様々なガンプレイを我々に見せて喜ばせてくれる。
マイト★ガイ旭の魅力 ●喧嘩・歌・旅・ガン● 佐藤忠男
小林旭とはどんなスタアか? その特徴を思いつくところから順にメモしみよう。
■活劇俳優である。(中略)階段をあがったと思うと、手すりを飛び越えて床へとびおり、そのままよろけもしないで格闘ができる。運動神経が抜群。
■美男とはいえない。しかし、いい男ではある。ねじり鉢巻きがよく似合う。下町のあんちゃん風である。
■熱狂的なファンがいる反面、あたまからバカにして見ない人も多い。そういう人がたまに見ると、なんてキザな俳優だろう、とたいてい言う。キザは、安っぽさであり、また新しさでもある。要はそれを、どうキャッチかするかによって評価が変わる。
■そのキザっぽさのきわまるところ、彼は西部劇をそっくりそのまま移し替えることをヘッチャラでやってのけた。そこには、アメリカの占領下に西部劇とマンガ本で育てられた世代の気分があふれていた。
■宍戸錠と組んで、日本映画で初めてピストルの撃ち合いを映画の見せ場として確立させた。
■そのノドが、なかなかいける。「風に逆らう流れ者」では「ダンチョネ節」だったが(*管理人注:初出は『海から来た流れ者』)、甲高い声のひょうきんな節回しに特徴がある。
■“渡り鳥”“流れ者”シリーズは、ある意味では、沓掛時次郎や、関の弥太っぺの再現だ。ただ、昔の股旅ものは、凶状持ちか何かでやむなく長いワラジをはいた。旭の“渡り鳥”は、レジャー活用の日本一周無銭旅行の趣だ。
■さて、以上を要約して、小林旭映画の魅力を探ると・・・
1. 旅 2. 歌 3. 喧嘩 4. ピストルの撃ち合い
まずは、喧嘩。
「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉がある。余談だが、国語学者の柳田国男の説によると、昔の都会人が喧嘩を好んだのは、それが社交上の利益を伴っていたからなのだそうである。
芝居や相撲とか祭礼とかで、よく喧嘩が起こる。これがどちらかがのされる前に仲裁人が入り、まあまあと酒の一献でも酌み交わし、お互い仲良くしゃんしゃんとなる次第。見知らぬ相手と知り合いになるには、これが手っ取り早い方法だったからだそうである。(中略)
小林旭と宍戸錠の関係なんかがそうだ。見ず知らずの間柄がピストルをつきつけあっている内に妙な友情が生まれ、そして一番の相棒になる。
続いて、歌。(*ここは詳しく)
小林旭に共通した雰囲気を持っている歌手、俳優は、アメリカのエルビス・プレスリーだと思う。ロカビリーと日本の民謡調とではまるで方向が逆みたいだが(*管理人注:当時は洋楽アレンジであるということに多くの人が気づいてなかった)ロカビリーだって元来はアメリカの民謡からきている。
プレスリーの歌は、歌それ自身もさることながら、体の動きのリズムに大きな魅力があるのだし、小林旭も活劇俳優の中では、もっともリズミカルな身のこなしを身につけた一人である。
小林旭の先輩格の石原裕次郎。そして、プレスリーの先輩格のジェームス・ディーンなども身のこなしの柔軟さで出色のスタアだったが、この二人の動きには、満場の観衆の視線を一身に集めている誇らしさがあり、みんなの喝采に対しては、会心の微笑をもって答えるという風な、スポーツマン的な、あるいはお坊ちゃん的なやさしさがあった。
ところが、プレスリーや旭には甘さはない。ジェームス・ディーンなら、初めて出会った相手に対しては、ちょっとテレたような表情で、わざと不良っぽいポーズをとってみせるだろう。
石原裕次郎なら、いささか気に喰わないと思う相手にも、最初は、やあ! と肩でも叩いて、自分の器量の大きいところを相手に納得させようとするだろう。こっちには敵意はない、お前の出方ひとつだぜ、仲良くしようや。ま、お前にその気がなければ、こっちも強いて友達になろうと思わないがね、というところだ。
ところが、旭やプレスリーの場合、気にくわない相手には、はじめっから敵意十分の顔でつっかかって行く。そういうところが、いかにもアンちゃん風で威勢がいい。
プレスリーの歌は、青春の欲求不満を世間に叩きつけるように歌うところに魅力があるが(*管理人注:ラスベガスでショーを行う前の若い頃のプレスリー)、同じように旭も、悪党どものキャバレーに乗り込んでゆくとき、ギターを抱えて挑戦するような歌いっぷりをするところが、馬鹿馬鹿しいようだが、断然見せ場である。
旅。
西部劇独特の、あの鹿革服みたいなのを日本映画に最初に持ち込んだのは小林旭だろう。
あの派手な衣装がきっかけで(*管理人注:『口笛が流れる港町』から)、日本版西部劇が生まれた。大人は驚いたが、子供はちっとも驚ろかなかったらしい。マンガ本で、そんなことは既に常識だったからだ。
ピストルの撃ち合い。
日活撮影所へ行くと、小道具係の人たちが、本物そっくのピストルを分解して、その中に電池を入れたり、電線を通したり、銃口からうまい具合に火花が散るよう、念入りに細工をこらしている。いかにもさっそうとして見えるけれど、あれはすべてオモチャです。ごあんしんを。
『大草原の渡り鳥』で逃げる悪玉の金子信雄を追う小林旭と宍戸錠。宍戸錠が卑怯なやり方は嫌いだと、自分の銃を金子に投げる。すかさず旭が錠にさっとピストルを放り、それを手にして撃つ。以後、日活のガンプレイは、もっぱらこの方法の応用であるようだ。
この他、品田雄吉氏の「西部劇入門」で、“渡り鳥シリーズ”からアメリカ西部劇の魅力までの解説。南部僑一郎氏の「無国籍映画の国籍」などが掲載されています。
|