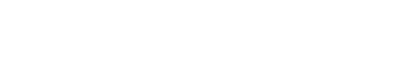アウトローからのメッセージ 日活アクションスター・監督論
(一部省略)
"渡り鳥”シリーズの原点は股旅ものに求められる。いっぽんどっこの風来坊ヤクザが富士山をバックに土手を合羽からげて走り抜け、三波春夫か白根一男の唄が流れる、ただそれだけである種の日本人にはじんとこみあげてくるものがある。しかし、これではあまりに純日本的で時代の変化に耐えることはできない。そこで、底辺に共通する心情的パターンだけを抽出して、強引に現代アクションの中にとり入れたのが "渡り鳥”シリーズである。ところがこの強引さは、<お茶漬けウエスタン>ともいえそうな妙なチグハグさを生みだし、えも言われぬ不思議な世界を作り上げた。
佐々木小次郎が物干しならぬギターをしょって馬で現れたような小林旭に、宿敵宍戸武蔵が一手所望するするのはまだしも、田舎だというのに銀座顔負けの豪華なクラブがあって、そこでは毎晩一流ダンサーのショーが繰りひろげられ、立派な紳士淑女でいつも満席。しかも、その裏ではカジノもどきの賭博場がひらかれ、麻薬が取引されている。そこへ、いかにも場違いな流しが入ってきて、ことわりもなく<ダンチョネ節>なんかを歌い始め、止めに入った用心棒も一曲終わるまでは手持ちぶさたそうにじっと待っていて、終わると同時に客からの歓声があがり、用心棒も行動を開始する。弱きを助け、強きをくじくヒーローの行動も、やむにやまれぬ怒りなどといった強烈なものではとんとなく、小犬に噛みついたブルドッグを後ろからけとばす程度のたわいないものである。なんといういいかげんさ!
問題は、思い切り場違いな設定の中で、場違いなヒーローが、場違いなアクションをして、一人で悦にいっている楽天的な姿にある。これはアクション映画を愛する観客自身の現実の姿である。オーバーであればあるほど恥ずかしく、それゆえにしごく可愛いのだ。裕次郎はカッコイイが愛せない。旭や錠はカッコワルイ(総体として見た場合)が愛せる。この違いである。

(中略)
"渡り鳥"シリーズがマンネリ化のいちずをたどりながらも、なおかつ人気を失わなかったのは、一に徹底したアクション、二に卓抜なアイデアによるギャグ、三に旭と錠の絶妙なコンビ、四にキザさと泥臭さのチグハグな組み合わせの妙、五に迷うことなく同一のパターンをくり返したこと、六にその底抜けのでたらめさなどがあげられる。
当時、松竹では大島渚を筆頭にヌーベルバーグ旋風が巻き起こり、東映では沢島忠や加藤泰らが新しい時代劇に闘志を燃やし、大映では森一生、三隅研次、池広一夫らが意欲的な時代劇を作り始めていた。しかし、"渡り鳥"シリーズなどの日活アクション・コメディは、ほとんど彼らとは無縁のところで完成度を深めていた。それは小林旭、宍戸錠という人間味のまったくないアクションの権化ともいえる逸材を得たからにほかならない。旭は懸命に滝伸次という桃太郎的偶像になりきろうとし、錠はひたすらマンガ的になろうとして、数珠を持ったり、ポップコーンを食べたり、神父の扮装をしたり、奇妙きてれつな殺し屋スタイルを生み出す。 ↗
"渡り鳥"シリーズは絶対に喜劇ではなく、ある意味ではまじめなアクション映画である。新興のボスにいじめられる土地っ子は深刻に悩み、ヒーローに好意をよせる浅丘ルリ子は真剣に恋をうちあける。このような多少緊した空間の中に、およそ不まじめ極まりない絶妙なコンビがが登場して、他人をほとんど無視した二人芝居を始める。
「あんた誰だい」「俺を知らないようじゃ、てめえも拳銃使いとしてはモグリだな」。同じアクションコンビでも"昭和残俠伝"シリーズの高倉健、池部良とは比較にならない荒唐無稽さである。二人のかけ合いによる名セリフは、観客の情感に訴えるものではなく、漫才におけるボケとツッコミのように調子を得たテンポの面白さでしかない。しかも、これまでの日本映画にはなかった、およそ生活者的心情を無視した歯の浮くような講談調の会話は、(意味)ではなく、あくまで紋切型の言葉の妙だけを追求する。当然、アクションも徹底的にこけおどしにやる。しかし、そこには、西部のガンマンほど風土に同化した説得力はない。いわば背広を着た忠次や助六といったところである

第六章 醒めた道化師の世界 日活活劇の周辺
(一部省略/宍戸錠についてが書かれている)
宍戸錠が喜劇人か!---と、六十年安保のころ、日活映画のなかで、さっそうたる殺し屋ぶりを見せていた宍戸を憶えている人は叫ぶであろう。だいいち、私自身、彼をこの文章のなかに登場させることに、大きな抵抗を感じているのだ。(中略)
そもそも、シンジケートにやとわれる殺し屋というのが、わが国では虚構のきわみである。
彼が<脇>であったころには、目を細める独特の笑い方だけで、あるリアリティを確保できたかもしれない。だが主演格になって、同じような(しかも、それは日活製メルヘンの中にのみ存在する職業である)を繰り返すことになったら・・・?
ここで宍戸錠が考えたのは、自分の演ずる人物が、まったくのフィクションであることを強調することによって、逆に、役の存在理由を主張するという方法である。
私の知る範囲において、宍戸錠はつねに醒めた人物であり、自分を突っ放して眺めることのできる珍しいスターである。
この醒めた道化師が、小林旭という無意識過剰(作者傍点)のスターとぶつかるとき、1+1=3といったおかしさが生まれた。
小林「ちぇっ、キザな野郎だな」
宍戸「むしろ、文学的といっていただきたい」
----といったやりとりが、このコンビの映画の核心となっていたし、
それがウケるとわかると、殺し屋が、
「どうも雑用が多くて、いけねえ」
とか
「俺は感情に起伏がねえほうでな」
といった名せりふを吐くにいたる。
当時、彼は、シナリオに書いてある以上のことを考案するのがむずかしいとこぼしていたが、観客側の感覚のエスカレーションと競争していたのは、宍戸錠ならでは、と私は思う。
おかしさはせりふだけではない。
『南海の狼火』ではジュズを持った殺し屋、『大暴れ風来坊』では神父姿に巡礼笠をかぶった殺し屋、というふうに
、紛争がエスカレートしていって、『大草原の渡り鳥』では、ついに北海道で西部劇そのままのアクションを演ずることになった。
台本も演出も、出演者の演技も、型どおりであるだけに宍戸の怪演は異彩を放ち、次はどのような扮装であらわれて、どのようなせりふを呟くか----いや、いつ登場するかということすら話題になったのである。 ↗
すなわち、ギャグを含めたさまざまなアイデアを持ちこむことによって、彼は、パターン化した日活活劇を冷やかし、批評し、真にユニークな役者となっていった。<笑わせる殺し屋>という、それ自体、矛盾した役柄を、極限まで広げることによって、<エースのジョー>という、いまだに通用するイメージを創造したのであった。
昭和三十五年にピークをきわめた日活アクションは、三十六年初めに、裕次郎の怪我と赤木圭一郎の死で挫折する。宍戸錠の主役への昇格は、興行上の必要でもあった。
第一作、『ろくでなし稼業』を終えた彼は、こう語っている。
「でもまあ、今年たぶん、まだこれからずっと主役みたいなことになるわけですけれどもね。つまり、あまり自意識なしにね。僕は僕なりで、まあちょっとインテリがみれば、あいつぁバカなことを・・・バカだねえ(笑)・・・ということをやって、それを狙うしかないと思うんですよ。またああいうところへきて歌なんか歌っちゃって、いやだねえ・・・という。でも、あいつバカだねえ、どうしてああいうことをするんだろうというこてゃ、決して軽蔑じゃないものね」
三十六年三月に封切られた『ろくでなし稼業』は、ヒットし、好評でもあった。「映画評論」誌ではこの年のベスト10に入る出来と評価した。

<注>掲載について不適切であれば、お知らせ下さい。削除をもって対応させていただきます。
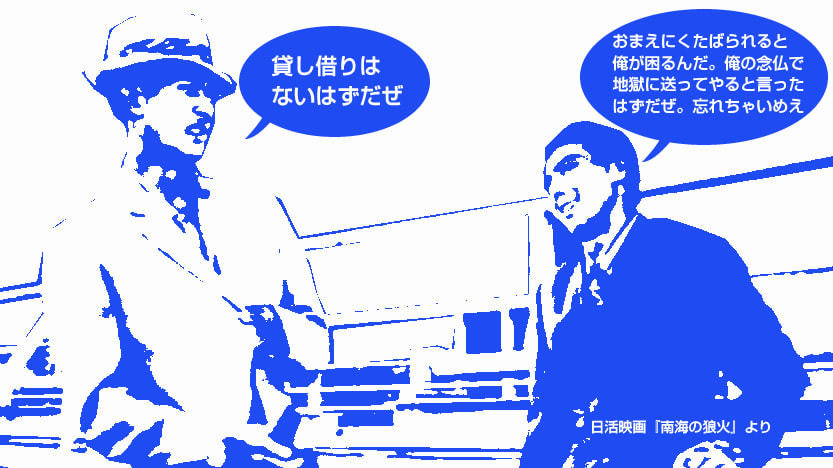
野村「お前何だって こんなところに来たんだ」
政 「決まってらぁ おめえを助けによ」
野村「貸し借りはないはずだぜ」
政 「お前がくたばられると俺がこまるんだ。
俺の念仏で地獄に送ってやるって言ったはずだぜ。
忘れちゃいめえ」
野村「お前とはやりたくねえよ」
政 「そうはいかねえ
お前のお陰で一生楽に暮らそうという俺のプランが台無しだ
食いもんの恨みは恐ろしいぜ」
日活映画『南海の狼火』より