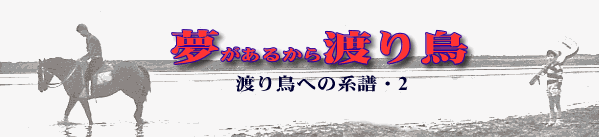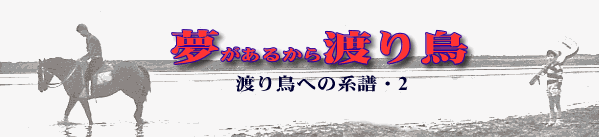●印象に残る初期作品
ものすごく印象深く残っている作品は『絶唱』(滝沢英輔監督)であると語る旭さん。「あの頃の日活の中ではもっとも優秀な監督の一人です。巨匠ぶらないし、それでいて緻密な計算が立てられる人でね、なんかみんなのために骨を折っているという感じだった」
●日活隆盛の期待を背に受けて
昭和33年の正月映画は裕次郎さんの『嵐を呼ぶ男』が空前のヒット。本格的な裕次郎ブームがやってくる。その後もたてつづけにヒットを出したが、やや勢いが止まる頃に代わって登場したのが旭さんの『南国土佐を後にして』(1959/斉藤武市監督)が大ヒット。急遽、会社は「小林旭で行こう」となった。勝負玉は『ギターを持った渡り鳥』(1959/斉藤武市監督)これが続いてのヒット。向こう三年間は日活も笑いが止まらなかった。
●敵が多いあいつ
(以下は旭さん談)
そのうち裕ちゃんが脚を折ったり、赤木がゴーカート事故で亡くなったりして、小林旭が一番使い勝手がよくて丈夫だわいということで、シリーズものだけで五、六本持たされて無茶苦茶に使いまくられた時代ですよ。それで若いから前の晩につい遊んじゃうんで、朝起きるのがしんどくなって、撮影現場に遅れて行ってしまう。多少は時間の余裕をみてよとこっちは思っても、なんだ三十分も遅れて来やがってと険悪なムードになる。だから、現場での評判は悪かったよね。僕は自分の気持ちをストレートに出すほうだから、気分が乗らなければそのまま抵抗しちゃうという面があるんだけれども、それでも自分なりにコントロールしながら抵抗してきたんだよね。だから、ここまで持ったんだと、やって来れたんじゃないかと思う。
●旭氏大いに語る
(以下は旭さん談)
それこそ大会社の会長や社長が一ヶ月で使うような金額を、一晩でバカ騒ぎして使ったんだから。だけど、それが仕事で溜まったストレスを発散させて、次の日の仕事に気分良く入っていく方法でしたかなかったし、一つの社会還元じゃないかみたいに思っていたんだね。そりゃ一般の社会常識感覚からすれば、それだけのお金があるんなら、たとえば社会救済するとか、なんか世の中に役に立つものに使えばと思うんだろうけど、でも、それをやったら「渡り鳥」の小林旭は生まれなかっただろうし、育たなかったと思う。大衆の娯楽である映画、その中で生き続けるアクション・ヒーローというものを演じられなかったんじゃないかな。ふつうの青年俳優で終わったろうね。
昔の自分の映画を見ると、なんていい加減な仕事をしているんだろうと思うようなところも確かにいっぱいありますよ。だけど、あの時には自分なりに一生懸命だったんだよね。アクションなんかでも吹き替えを使わずに全部自分でやっていたし、命がけの時もあった。だから、作品の特異性とか名作がどうとかいうのは、あくまでもプロデューサーや監督の感覚で選び製作するんであって、こっちは選ばれた商品として一生懸命にやれば、次の仕事がまた来ると、その当時はそう思っていたよね。
●旭氏自身の企画へのこだわり
後に旭さんは自分自身で企画を提案するようになった。さいとうたかを作品の「無用ノ介」や「ゴルゴ13」の劇画が好きだった旭さんは、日活に「ゴルゴ13」の映画化を提案した。まだ、ブームの前の話である。会社はさいとうプロに交渉の後、金がかかり過ぎるということでボツとなった。その後、コミック誌の劇画ブームが起こり、東映が『ゴルゴ13』(高倉健さん主演)
を映画化。アクションの切れは小林旭氏以外に、ゴルゴ13にうってつけのキャストは居ない(当時は)。
<参考書籍:「日活 1954-1971 映像を創造する侍たち」ワイズ出版>