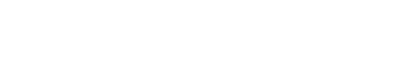小林旭=衰えぬ不滅の肉体 斎藤武市
- 石原裕次郎が、デビュー後間もなく、アウトロー世界から市民社会へ、いったん移行してゆくひとつの契機になったのは、いつまでも”裕チャン”、太陽族の弟でもあるまい、という年齢的配慮と、元来肥満体質らしい彼の、肥り過ぎではなかったかと、俺は推測している。
- デビューした頃の裕次郎は、主演作の画面に、まず脚から登場する、ということがあった。それほど彼の長い脚は、魅力的だと考えられていたのだ。その長い脚の片方をバスケットか何かで傷めたとかで、引きずり気味に歩くのも、当時の言葉で言えば、イカしている、ともてはやされる材料になっていた。
- これは、それからの二十年間で、日本人の体型が、急速に欧米人に近づきつつある今からすると、ちょっと想像のつかないことかも知れない。しかし、事実はそうであり、裕次郎は、その長い脚を”マンボズボン”に包んでフレーム入ってきたりしていたのだ。
- その長い脚に、肥り気味のボティが乗っていたのでは、自慢のアクションも、もうひとつパッとしないことと、それから先も、確実に年齢を重ねる、という展望の中で、第一の転身が企画されたのではないか、という推測は、あながち考えすぎではあるまい。
- このように、常に肉体をさらすことを前提にしたヒーローが、自らの肉体に裏切られてゆく瞬間には、俺たちの想像を絶した、どえらい葛藤があるのだろう。そんな現実に直面しながら、なお、それを回避ることを許されないヒーローは悲惨だ。そしてむろん、この時、ヒーローをヒーローとして支え続けようとする観客の視線は、あくまでも残酷なのだ。そしてこの、観客の無意識なサディズムは、自らがヒーローになり得ることはない、という悲惨さに支えられている。
- 小林旭の、何年ぶりかの主演作である『多羅尾伴内』(鈴木則文・七八年)を見ながら俺が思ったのは、ああ小林旭は不滅だな、ということであり、ヒーローにおける肉体と心理ということだった。

・関連サイト内リンク:多羅尾伴内
http://www.8107.net/akira/bannai/
- 昨年、ある雑誌で小林旭特集の企画が上がった時、声をかけられた俺は、迷わず小林旭の肉体論をやりたい、と申し入れ、旭における肉体のツヤ、とりわけうなじの色っぽさが、十代から不変である奇跡について、熱っぽく語ったおぼえがある。
- 結局、その企画に俺は乗せてもらえず、あんまり吹くからホモだと思われたのよ、という酒場の女の冗談で一件落着したのだった。しかし、小林旭はすごいのだ。
- 鈴木則文には、馬鹿バカしいことを面白がってしまい、そのことが結局、観客へのサービスになってしまうという、奇妙な才能があり、片岡千恵蔵で人気があったこの作品のリメイクにおいても、まったくてらわず、馬鹿気た、といってしまえばそれ迄の七変化を、堂々と見せてしまう。
だが、その時にスクリーンに身をさらし、文字通り見せているのは、小林旭なのであり、特筆すべきは、まるで昨日迄『銀座旋風児』(野口博志・五九年)だった男が、そのまま多羅尾伴内になったかのように生き生きと演じて、いささかもおとろえを見せない、旭のツヤ、色気なのだ。
肥満ということなら、旭も裕次郎に負けぬほど肥ってしまった。そして、この肥満する過程では、食事制限でもしたのだろうか、色艶のよくない顔でヤクザを演じた『縄張はもらった』(長谷部安春・六八年)などは、それがむしろ凄味になっていたこともある。そんなところは、何ともトクな俳優だ、とでもいう他にない星廻りに支えられている。
だがしかし、それは単に星廻りということだけのことではない。同じように肥満しながら、裕次郎のそれが、無惨な風化という他ないのに反して、旭の場合、みごとにツヤを失っていないのは、旭の側にあっては、ただの一度も、自らがヒーローであることを疑ってみようとしなかった、心理的な張りがあったからのだと思う。
かつて、『渡り鳥』シリーズで絶妙のコンビを組み、自意識過剰風に演技してみせた宍戸錠に対して、小林旭を”無意識過剰”と看破したのは、中原弓彦こと小林信彦だったと記憶するが、この、小林旭における無意識過剰とは、スター意識、ヒーロー感覚の徹底性なのである。
むろん、こうしたあくことなきヒーロー志向は、小林旭の内にあっても、肥満してゆく過程で、根底からおびやかされたことがあったはずである。その時、スター旭が抱いた矛盾は、まさに選ばれてあることの地獄という他はない。しかし、この人がすごいのは、どのような局面にあっても、俳優としては転向しようとしなかった不退転の決意があったろうこと、これなのだ。
そして、この決意が支えているヒーロー像が、前出の『銀座旋風児』をはじめ、『流れ者』・『渡り鳥』シリーズという代表作と、かつて他人が演じた代表作を担ってもなお一直線に連なり、何の変更も加えられずにいる点において、小林旭は不滅なのであり、戦後ヒーロー史に照らしても、形容しようのない突出ぶりを示している。
俺は確信を持って断言するのだが、小林旭は、死ぬまでヒーローであり続けるはずだ。むろん俺は一人の観客として、他ならぬ旭に残酷にそれを押しつけるのだが、この人がヒーローの座を下りる時は、俳優をやめる時でなければならない。
そして、おそらく、このことは旭の内においても確信されているはずなのだ。失敗しては話題を呼ぶこの人の事業意欲の根拠は、そういうことなのだと思う。この眼配りがセコく映らず、ヒーロー像の風化に直結しないのは、そこまでしてスターの座を抱いて死のうとする自意識を、みじんも感じさせずに、スクリーン上では無邪気という他ない荒々しさをもって肉体を投げ出し得る、無意識の回路があるからなのだ。
このように、しょせんは亡びるしかない肉体の内に自らのヒーロー像を秘めて、肉体を過信し続けようとした旭と、それができなかったフシのある裕次郎との違いは、あまりにも大きく、この落差は、何をもっても埋めることができない、決定的なものである。