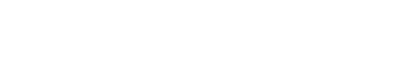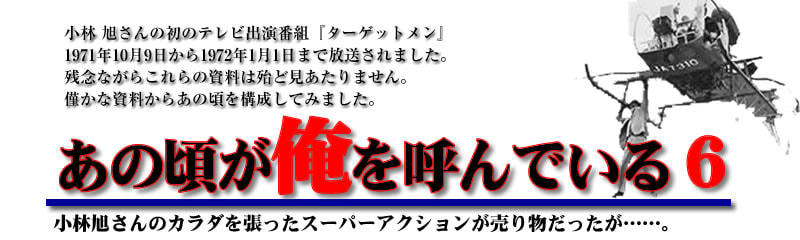マイトガイ小林旭 まだ健在
高度15メートル、時速30キロのヘリコプターから小林旭がナマ身を空中にさらし地上を走るトラックに飛び降りた。12日埼玉県・浦和市郊外で行われたNETの新番組「ターゲットメン」(10月9日スタート、土曜午後8:00)でのアクション・シーン。格闘あり、撃ち合いありの本格的アクションに、小林旭は「ヘビー級のスリルをお見せすると、胸を張って“マイトガイ復活宣言”をやってのけた。
浦和市といっても、志木や朝霞が目と鼻の西はずれ、荒川川原にある秋ヶ瀬公園から、一機のヘリコプターが飛び上がった。操縦席の外、ソリの部分に一人の男がぶら下がっている。小林だ。
15メートルの低空で旋回しながら、地上に現金輸送車を発見するや、猛然と襲いかかる。みるみる接近。砂煙に包まれながらヘリから車の屋根へ、一瞬の早わざで飛び移った。NETでは5,000万円の保険をかけた。
「私は撮影の仕事をずいぶんやってますが、度胸じゃ、あの人(小林旭)が一番。高度15メートルといえば、人間が一番恐怖を感じる高さで、ましてヘリはコクピット(操縦席)が透明で足元まで丸見えだから、カメラマンなんかたいていしりごみする。それを彼は、機体の外に平気で出ちまうんですからねえ」(パイロットの日本農林ヘリコプター、佐藤将富さん)
この日のロケは第6話の撮影。奪われた三百六十億円入り現金輸送車を取り戻すべく、捜査官中西五郎(小林)が空から出動するシーン。“地上”での撮影が終わると、汗かきの小林はシャツごとシャワーを浴びたよう。しかし、疲れた様子もなく「さあ、今度はヘリだ」と忙しく動き回る。
アクションの型からカメラの段取りまでテキパキ決める。かと思うと、輸送車を撮影場所まで、自分で運転して移動させる。そのペースに、付き人の方がオロオロ、「ある意味で、やりやすいんです。演技的ななことはもちろんスケジュールのことまで、なんでも小林さんに聞けばわかるんですから、めんどう見もいい人だし……」(共演の奈美悦子)
日活であばれまわっていたころから十年たつ。「なんといってもキャリアは人に負けませんからね。自然にやっていれば“小林旭”型のアクションがにじみ出てくるはず。“キーハンター”の千葉(真一)君とよく比較されますが、彼は彼なりの華麗なアクション。からだは彼の方が軽いでしょうが、僕は、なぐれば相手が本当に倒れるような、ナマのアクションをお見せします。」自信満々なのである。
撮影は、もう五月から始まっている。六階建てのビルからビルへロープで渡り、手の平をすりむいた。二十メートルのガケからころげ落ち、ヒザを折った。
「僕は一日中セットの日はエネルギーが余って調子悪いんです。アクションこそ僕の武器。恐怖なんて感じません」昼休み、グイッとオレンジ・ジュースを五杯あおった。かつて、航空自衛隊の教官から「抜群の平衡神経」と折り紙を付けられた。“マイトガイ”は衰えていない。
昭和46年8月13日(新聞紙名不明)
■1971年10月9日〜1972年1月1日まで 13回放送

|
サブタイトルを見ると、なんとなく見覚えがあるようなものが並んでいますね。当時、リアルタイムで見た記憶はかすかにありますが、明確には憶えていません。