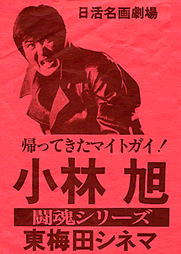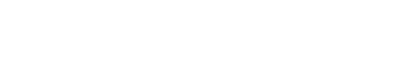ヒーロー渡り鳥 小林旭の世界
日本映画だけの雑誌「シネマぱらだいす」は、幻の雑誌で詳細は知りませんが、日本映画のみをとりあげた(といっても偏りがあります)大阪の出版社で1977年頃に創刊されたようです。主として東映と日活映画を中心に紹介されています。販売場所は大阪の映画館を中心に一部東京でも販売されていました。私が本誌を手にしたのは大阪梅田の紀伊國屋書店でした。
当時まだ若かった私は子供の頃から憧れ続けてきた小林旭さんの特集、特に渡り鳥が帰ってきたことの喜びで心の中で躍ってました。
なにしろ、渡り鳥•流れ者関連の情報なんて無かったですから。うらびれた映画館で、たまにかかる渡り鳥映画を求めて通った時代です。現在のように簡単にビデオ映画なんて見られません。そんな状況からこうした雑誌が生まれ、併せて旭さんの映画特集が組まれるのは夢のような事でした。
そんな雑誌から当時の旭さんの心境をインタビューされた記事が掲載されています。その中から抜粋して以下に掲載します。


1977年頃に発行された(時期あいまいでスミマセン)「シネマぱらだいす」の中で旭さんの永年のファンである高橋聡氏という方のインタビューが掲載されています。この高橋氏は私と同じ「渡り鳥・流れ者」にこだわりをもたれているようで、そうしたことが後記の締めの文章に書かれています。
その後記の文章から紹介し、インタビュアーの高橋氏の熱い思い入れを前提として本文の一部を紹介したいと思います。
〔インタビュアー・高橋 聡氏の後記〕
青春時代を誇れる人は幸せである。日活アクション映画に青春を賭けた役者・小林旭は過去の栄光に誇りを持っている。アキラ映画で青春を過ごした者にとって、アキラは単なるスーパー・スターではない。あの日、あのころの時代の鏡でもある。
小林旭に会うことは、自分自身の、あのころに会うこと。そして、これからの人生に夢を持つこと。
(インタビュアー・高橋 聡)
----ここに約150本近くの小林旭フィルモグラフィーがあります。児童劇団から日活ニューフェイスとして映画界デビューしたころの話から…。
『日活に入った時分のボクは、映画で芝居をするということに、単純に魅力を感じましたね。たとえば、自分のうしろ姿がどういう具合で、どんな歩き方をしているのか、それを見たいと……当時はビデオも8ミリもなかったですからね。映画というものに憧れてましたよ。初めて自分のうしろ姿を見たときの感動というのはいまだに忘れてないしね。大変なショックというか感銘というか。56〜57年のころというのは、台本をもらい、セリフをを読み、映画の中で芝居するのがたまらなく楽しかった。他は何も考えなかったですね。
1〜2年経ってくると、芝居にプラスアルファというか自分の個性をどう表現するかみたい」なことを考え始めました。57年の『孤独の人』『殺したのは誰だ』『青春の冒険』『九人の死刑囚』というのはボクの代表作えすね。そのころは映画の芝居に大変な興味を持ってて、共演している人が左幸子とか金子信雄さんとか一流の役者さんが揃ってましたから、左卜全さんもいたし、その中で自分の分野を開拓していこうという気で……』

「シネマぱらだいす」第4号を見る小林旭さん(特別号より)
----ヤル気満々の野心的な新人ですね。
『56年のころまではエキストラの仕事をずっとやらされていて、57〜58年になっても、主演をやりながらも仕出しの仕事をやってますからね。ニューフェイスで入るとまず大部屋に所属するんですよね。そこから1歩1歩始めていくという、昔ながらのシキタリだったし、我々もそれはやらされました。きびしかったですね。裕次郎の場合は、57年の半ばから現れたヒトですよね。あのヒトは突然出てきて『幕末太陽傳』や『錆びたナイフ』をやったラッキー・ボーイだから。彼の場合は特待生ですね。我々は主演作を撮りながらあくまでも仕出しの分野もやらされた。59年の『若い豹の群れ』のころまで続きましたね。そのあとの『爆薬に火をつけろ』からマイトガイとして売り出されることになりますね。それにつづいて『南国土佐を後にして』が大ヒットして、それから「渡り鳥」「流れ者」シリーズにつながっていく。それからは小林旭は完全なスターになりますね。主演作しか撮らないスターにのしあがって。ここまでくる4年間というのは主演と仕出しをいっしょにやってる状態だったですね』
----『絶唱』とか『完全な遊戯』で主演をやったスターが仕出しもやってたなんて信じられない話ですね。
『そのころはそうしないと生活できないような状態の給料だったわけで。1日も早く車に乗っかって撮影所に通うような大sターになろうという意欲は、悶々と燃えてましたからね。この時分に目標というか、うらやましいなあと思ったのは、三橋達也であり、水島道太郎であり、南田洋子さんとか、ベンツに乗っかって来る人達でしたね。ボクが車で撮影所に通えるようになったのは59年の半ばころからですね。ギャラ・アップもそのころから百万の声を聞くようになったから……』
----初期の作品で印象的なものは?
『そうですね。ボクのアクションものの最初で『夜霧の第二国道』ですね。学生映画で秀逸なのは『美しい庵主さん』で。青春ものでは『踏みはずした春』で、これは浅丘ルリ子とのゴールデン・コンビというか、何度かいっしょに出てたけど、コンビらしいコンビはこれが初めてですね。 文芸大作の本命中の本命が『絶唱』だね。学生不良映画の『完全な遊戯』も、演技開眼というか…。やった! という気があったけど。『殺したのは誰だ』で蓄積していたものを出したということですけどね。その後は、ムードにに乗っかっていってプログラムピクチュアにも乗っかっていくんですね。シリーズ男誕生ですね』
----月1本ペースになりますね。撮影日数は20日間ぐらいで大変なハードワークだったのでは?
『若さですよね。平気な顔をしてやってましたからね。ボクはロケーションの多い役者なんですよね。『絶唱』は松江だったかな?
----シリーズものが多くなってきて、そのヒーローの演じわけ方というのは?
『ヒーローは違っても、やってる本人は同じ人間だから、結局、見た目で変えよういうことで、「渡り鳥」のかっこというのはきまりの西部劇スタイルでいこうと、「流れ者」は、ウェスタンに出てくる流れ者ではなくて、その町の中にいる農夫のスタイルといった感じで。「渡り鳥」というのは完全なさすらいのガンマン・スタイルで。「流れ者」は町に定着した人間の農夫的な拳銃使いの男の感じという具合に。だから、頭のカッコウも違うし、衣装も違うし、その程度でわけるしかなかったね』
----無国籍の感じも段々とエスカレートしていくわけですね。
『いや「ギターを持った渡り鳥」や「波止場の無法者」が封切られたころには既に南部さん(*南部喬一郎さん<映画評論家>:管理人註)あたりの口から「無国籍な映画」だとか「不思議なウエスタン」が出てきたとか言われて。「口笛が流れる港町」がその最高のものじゃないかな。60年に入ってかrはその余勢でやってましたね』
----毎回の趣向が大変だったでしょ。
『映画というのは、服を変えてやるのは当たり前だし、現実の問題として。1本の作品で同じ服を必ず2着作ってましたけど。そうしないと破けちゃいますからね。必ずアクション・シーンで。道路にスライディングしたりして……』
----西部劇タッチの工夫はどうやって研究したんですか?
『その時分は、ジョン・ウェインの映画を見て、これはいいなというのを引用してみたり、あるいは他の西部劇を見て真似してみたり。西部劇が好きだったんですね。小さいころから活劇が好きだったし。エロール・フリン、タイロン・パワーも見たし、ハンフリー・ボガートの現代アクションを見て育ってきた方だから』
----ジョン・ウェインになったような気持ちで演じたわけですか?
『ジョン・ウェインの姿勢がとってもいいでしょ。ひとつのものを大事にして。俺は西部劇スターなんだと。ジョン・フォードから西部劇しか能の無い役者だからお前は西部劇以外にでるなよ、と。それを大事に守っていくと。あの意欲と姿勢。だから、ボクの場合も、いくつになってもアクションというものに命張って体を賭けてやっていこうと思いますね。体の動く限り娯楽アクションをやっていこうと。その気持はいまだに変わりませんね。
(*このスグ後には『多羅尾伴内』<1978年4月・東映>が公開される:管理人註)
----アクション映画での撮影で危険なシーンを吹き替えなしで演じたというのはいまだに語り草ですけどね。
『必ずといっていいくらい1作品で、それこそ命の保証はできませんよ というシーンがひとつはありましたね。もちろん、その場に応じて、自分でやれるという計算はありましたけどね。命まで失くすことはない、カスリ傷か骨折程度くらいだろうという計算があれば自分でやりましたね。40キロで走ってくる車に飛び乗ったり、オープン・カーの中にダイレクトに飛び込んでみたり。走る汽車から飛び降りて、自分の体がどの角度で弾むことが出来るかとか、この高さから降りたらどの程度のショックになるかとか……計算は年中やってましたね』
----長谷部監督がアキラさんが火に包まれて死んでしまったのじゃないかというシーンがあったといってましたが。
『ガソリンの量とか火の燃える火力みたいなものは計算できないところが出てくるし、計算外なこおも起こりましたね。でも、いま思い起こしてみると、わりに沈着冷静だったなと思いますよ。炎に包まれて、その中でも自分が何処へ逃げたら助かるかという計算をパッとするんですね。そのかわり、やる前に必ずまわりを見ていて、万一の場合はあそこに逃げれば助かるという具合に。それを記憶することですね。セットの中での格闘の場合でもボクは細心の注意をはらいますよ。大道具、小道具、照明部の連中を総ざらいでもってセットの床板のクギ、ガラスのコマひとつまで全部綺麗に掃除させてからヨーイ・ドンでやりましたね。カスリ傷、キリ傷はしょっちゅうで、毎回、2針か4針くらい縫うキズとか、全治10日間の擦過傷とかいうのも。体も丈夫でケガの治りも早かったから、なんとか持ってましたね。脂肪組織が強かったということでしょう。ケーツイの骨折と鎖骨の骨折くらいが大きなケガだったですね』
----「渡り鳥」シリーズやなんかでいろんなガンプレイが出てきますね。ジョーさんとのイキなやりとりも。
『毎回ありましたね。監督と殺陣師とジョーさんとみんな
で「ジャン・ギャバンのやったあんなシーンにしよう」とか。「恐怖の報酬」でいこうとか。スタイルの物真似もありましたね。ガン・プレイの練習は毎日やってましたよ。拳銃を腰にぶら下げて撮影所にいっては早射ちの練習をしたり、ライフルをいかにかるく扱うかという……。ジョンウエインがライフルを扱うとピストルくらいに小さく見えるわけ。ボクもずいぶん研究して練習しましたよ』
----ルリ子さんがいてジョーさんがいて白木マリさんがいた。
『パターンですね。中原早苗であったり白木まりであったり、笹森礼子であったり。相手が変わったけど。ヒロインが哀れな目にあうときにヒーローが必ず助けるというパターンはかわらずで、その根底に流れるものというのは勧善懲悪ということで、あれほど徹底した娯楽作品は無かったですね。理屈じゃないと。ギャングと射ちあいしてるのに何故が来ないのかなとか、それを考えると映画は面白くないのだと。映画というのは夢であり、架空の物語なんだから、世の日常の雑用を忘れて映画を見る人を楽しませることができるかということい努力したわけだから。最近の映画は、お客さんの方もそうなんだけど、そういう姿勢が失くなっちゃったということが映画の衰退した、面白くなくなった原因じゃないかしら。理屈の裏付けとリアリティーを求められるというカタチで「グレートハンティング」あたりがリアリティーの極をついてるもんで、それが大ヒットするわけだから……。不可思議な殺伐とした世の中になってしまったというのが映画が斜陽になった原因のひとつだと思うけど……』
----「渡り鳥」などのヒーローを演じるときにカッコよさみたいなものを意識してやるわけでしょ。
『意識はしますよね。ただ、どうやったらカッコよくなるかな、みんなが納得するスタイルになるかなということはいつも考えてましたね』
----アキラさんの最新曲。「北へ」の歌詞もそうですが、流れるということ、ヒーローに対するアキラさんの思い入れはどんなものでしたか?
『それは、いつでもボクはそうだけど、ヒーローとかヒロインだからということじゃなくて、どう楽しく見せるかなということを一生懸命考えることが我々の責任だと思うんですよ。カッコよさだけを追うんだったら表面だけで終わってしまうし、きれいに見せるだけの女だったら見飽きてしまうだろうし、そこにルリ子自身も、共鳴を感じ、リアリティーをもたせ、夢物語をいかに真実味あるものに見せるか、お客さんを納得させることができるかとというので努力してくれたことが「渡り鳥」の良さだったんじゃないかな。ジョーさんにしてもルリ子にしても監督にしてもボクにしても。「渡り鳥」一家といわれるように、何かにつけて私生活も接触していたよね。よく飲みに行き食べに行き、団体で行動してましたね。飲む打つ買うも……。そういうところでルリ子とボクの噂も出てきて、結婚するだろうということになって。四六時中、離れることがなかったものね。知らない人から見れば、風呂もいっしょに入り、ふとんもいっしょに寝てんじゃないかとみえるのも無理ないことなんですよね。それくらい密着してたけど、それはルリ子だけじゃなく監督もそうだったしジョーさんもそうだったし。密着の度が濃かったからよかったという部分が作品の中に出ましたよね』
----「暴れん坊」シリーズは、まったくリラックスしたアキラ・ルリ子の軽妙なタッチの喜劇だったですね。
『ちょっぴり「渡り鳥」がマンネリだといわれだして喜劇をやったらどうかということで。新分野の開拓ということもあったけど。ところがやっぱり、「暴れん坊」より「都会の空の用心棒」とか「太平洋のかつぎ屋」のようなハード・アクションの方がお客さんにウケたみたいだね。近代アクション・ドラマの始まりだろうね。「都会の空の用心棒」は。拳銃は使われず頭と体でアクションを見せて事件を解決していくという……』
----アキラ映画には必ず歌がありますね。
『59年の半ばからの作品は歌もアクションと同じような売りもののひとつになったということがあったよね。「爆薬に火をつけろ」からかな。歌う映画スターということで。わりに無責任に歌ってたね。いまでもそうだけど、歌は自分が楽しんで歌ってるから。映画は見る人をいかに楽しませるかということで違いますけどね』
----「賭博師」シリーズというのが次に出てきますね。これも無国籍の延長ではあるけども……。
『都会に定着した無国籍ものといった感じでしょう。ギャンブルは昔からしない方。マージャンをお付き合いでするくらいで。競輪、競馬を自分から好んでやるということはなかった。トランプのカード裁きやダイスなんかはよく練習したけどね。朝、セットに入ると片隅で毎日のように。ダイスも5つ並べてサッとやって立たせるのなんか、キャメラのカットをかえると面白くないと、斎藤武市さんが1回でできるまでやろうと。マガジンに2千フィートフィルムがあるけど、何度まわしてもいいからやろうと。ボクも負けず嫌いだから「よし、やろう」と。本番2回目でできましたね。その瞬間に、西村晃さんとか二本柳寛さんがかたずを飲んで見てるわけ。「できた!」という表情は芝居以上のものだったな。ダイスを5つ立たせたときは。あのときの西村晃さんの芝居はいまだに忘れないな。「さすが左ききの」という芝居になるのだけど、本当にやったのだから芝居もリアルで。あのときの感激は西村さんも憶えてるのじゃないかな(※「南国土佐を後にして」のワンシーン 管理人:註)』
----氷室浩次という男は、非情にリアルな存在ですね。人生が賭けであるという、賭けることに執着している。
『勝負に人生を賭けたという執着においては、ボク自身の人生の賭けという部分とダブってたこともあったですね。そんな現実的なことが出た部分も……』
----長谷部さんのデビュー作が「俺にさわると危ないぜ」で。
『そうそう。そして「縄張はもらった」とかね。ドキュメンタリー・タッチの狙いがとってもよかった。長谷部のやり方と気のあう部分多かったけど、狙い過ぎちゃっておかしくなったところもあるな。深作欣二さんなんかもそうだけど、自分の考えてる社会構造みたいなものを絵にしてみたいという意欲はよくわかるけど、もし、ボクが監督の立場であるならば、大衆にうける商業作品をやってても、立派に世界に通用することが可能な人じゃないかと思う。黒沢明さんが社会派だったかというとそうじゃないと思うし……。「サイレント・ムービー」のメル・ブルックスじゃないけど、大笑いさせながら、あとでお客にフト気づかせるという部分があるしょ。ブルジョワの生活を描いて「貧乏人を馬鹿にするな」といえば味が出るだろうし、貧乏人の生活を扱うからといって貧乏人の中にもぐり込んで撮っても……。そのへんで浦山桐郎さんが成功したというのは、前に「キューポラのある街」を撮ったけど、大衆娯楽の中に芸術が生きているのじゃないかということにどっかの接点で気がついているのじゃないかと思う。それで「青春の門」を撮ったのじゃないか。今村昌平さんも、現実的にあり得ないような話を実際にありそうなカタチでもってあらわしたから鬼才と言われるものじゃないかな。深作さんも「仁義なき戦い」でも、深作さんの社会構造がやくざ社会にもあったということで、あれだけの反響をとった……。山田洋次さんはが役の意味で立派ですけどね。日活の無国籍時代の監督さんも娯楽に徹していて立派だったよね。娯楽作品を撮るのは能の無い監督だというのは絶対になくて、それが一番難しいことなんだと思う。大衆をいかに喜ばすということは……世界の人間が黒沢明に撮って欲しいというのは、スケールの大きいものを平気で作ることと、芸術性を匂わせていて娯楽作品をとるという才能のあり方ですよね。臆面もなく西部劇のカッコを真似してみたり、「用心棒」なんか、平気で西部劇タッチで撮るというあの図々しさ、才能の素晴らしさ……』
----「用心棒」で思い出したけど、舛田利雄さんの「血斗」というのがありましたね。
『ああ、昭和時代劇で。あの時分は、「対決」もそうだけど、高橋英樹の売り出しで、ボクはカタキ役だったですね。だから、あんまりおぼえてないですね』
----非常にとぼけた味があって面白かったですよ。アキラさんの役は。
『だから、芝居としては無責任な芝居をしてたから逆によかったとか……。(笑)ボクとしては長谷部の「爆弾男といわれるあいつ」あたりから「女の警察」くらいの間まではちょっと抜けてるわけで。「縄張はもらった」以外は』
----鈴木清順さんの「関東無宿」で例のまっ赤になる名場面がありましたね。
『監督の狙いが鈴木さんとしてあったわけでしょ。小林旭の芝居と歌舞伎の所作ごとみたいなこととイメージをダブらせて…大立ち回りも平面的なセットを組んで、主人公が親分を斬り倒して、バックが血の色になるという、主人公の人生が血塗られたものであるということを絵で見せちゃおうという試みがあったんでしょうね。面白いことをするなと思ったけど、何を意味するのかわからなくって、「鈴木さん、どうしてこんなことをするんですか?」というと「まあ、いろいろあるんだよ」って。それより深くは追求しなかったですね。フィルムが全部つながってから、その狙いがわかったけど、そのときは理解できなかった。鈴木さんとは「踏みはずした春」からやってるから相当多いでしょ。そのころから才能のある人だと思ったし、面白い人だな、と。好きな監督さんですね。ボクは川島雄三さんや滝沢英輔さんが一番好きですけどね。鈴木さんも思い出に残るし、鈴木さんの下についてた野村孝とか長谷部安春なんかも好きだった。人間的にもね。鈴木さんには商業ベースに乗っかったいい作品をもっと運で欲しかったという気持はありますね』
----アキラさんのキャラクターの流れの必然性みたいなものを、たとえば「縄張はもらった」の存在感が「仁義なき戦い・頂上作戦」のラスト・シーンのアキラさんとダブってくるというか……。
『一作目で出したものを二作目では出させてくれなくなるということがあるね。監督というのは。もっと望むわけで。「仁義なき戦い」も最初の「代理戦争」の方が、文太とのからみで、人間臭さを出せるムードを作ってくれたよね。ところが二作目になると、それにたよるようなところが出てきて、違った面を出してくれみたいなことで、本当の味が薄れてきちゃう。ボクは「頂上作戦」はあんまり好きじゃない。「代理戦争」の方が武田明という役を掌握してやってたような気がするよね。「頂上作戦」になると把握できない部分が出てきた。』
----でも、「頂上作戦」のラストシーンは名場面で……。
『あのラストは、納得してやったというか監督の狙いと合ったということで。ここだけはという部分で…。監督と役者というのはウマのあうあわないもありますね。深作さんとはあう方だけどね。ウマがあい過ぎてノリ過ぎて失敗する場合もあるし、「無頼無法の徒・さぶ」を野村さんとやってるときがそうで「もっと、もっと」やって失敗したところがあったな。監督もボクも構えすぎてて。サクさんとやってみたい映画がある。鉄砲玉の話で。チンピラの方が本当のやくざの男の味というのはあるんだよね。馬鹿にされ、踏みくだかれても、スッポンのように食らいついていくような。ボクにチンピラがどこまでやれるかということは難しいけど。軽薄さからにじみ出る逆にヒロイックな面を出せたら面白いのじゃないかなと。この喜劇版が寅さんでしょ。「ダボシャツの天」(※管理人註;リンク)をもっとリアルにしたみたいな』
----71、72、73年というのは年に1本しか映画出演がないですね。
『日活と契約が切れたし、69年あたりににもそんなことであんまりいいものに出てないですね。扇ひろ子「昇り竜鉄火肌」とかオールスターの「博徒百人」とか、自分のものでは「やくざ渡り鳥・悪党稼業」なんて意味のないものをやったりして…。やっぱり一番燃えたのは59年の半ばから62年の間くらいでしょうね』
----最近、旧作を見る機会は?
『全くなし……』
----「仁義なき戦い」と「青春の門」で演技派・小林旭が見直されいるけども、その片リンは「完全な遊戯」のころからあったわけで……。
『スーパーマンになると演技力以前のものになるから……芝居をじっくり見せるというのじゃなく、いかに楽しく面白く見せるかというものが先行していたから。そういう意味では「仁義…」も「青春の門」も久しぶりに芝居をしたという感じがしたけども……』
----役者としての欲が出てきた時期は?
『それはやっぱり初めの頃だろうね。スターになろう。映画を撮るなら主演ものがズラリと並ぶようにしようという意欲で。絶対にスターになると。それがないと役者はダメじゃないかな。いい意味でのスター意識があるうちにお客さんにいい芝居ができるのじゃないかと……』
----自分の作品の好きな作品を10本あげてみて下さい。
『ウーン……「殺したのは誰だ」「九人の死刑囚」「絶唱」……それから「南国土佐を後にして」……「口笛が流れる港町」「都会の空の用心棒」「太平洋のかつぎ屋」「大森林に向かって立つ」……「夢がいっぱい暴れん坊」「俺は地獄の部隊長」「関東遊侠伝」「黒い賭博師」「縄張はもらった」「女の警察」「日本最大の顔役」といったところ』
----一番想い出深いものは?
『やっぱり「殺したのは誰だ」じゃないかな。芝居らしい芝居を要求されて、それまでいい子いい子だったから。不良大学生の役だったけど』
----これからの役者・小林旭は……。
『いいもの、楽しいものをどんどんやっていこうと。小林旭を見たいいう人にサービスしてあげたいという気がしますね』
----アクションは?
『楽にできますよ。いまの若い人にスピードと体力では負けませんよ』
(3月15日、東京・溜池クラウン・レコード本社地下のスナックにて)
帰ってきたマイトガイ! 小林旭
1978年4月2日〜6月3日まで、約2ヶ月余りにわたって上映特集されました。この映画館は当時の「にっかつ」映画館であり「にっかつロマンポルノ」がレギュラー上映されていた場所。そんなところで特集が組まれたのは異例でした。
当時の私はフリーランスの仕事で西日本各地を転々とする仕事をしていて列車の中では小林旭さんの歌をカセットテープで聴きながら渡り鳥気分にひたっていた頃です。そんな矢先でのこの上映会です。私は地方のあるお店の店頭でのデモンストレーションを行うことから当時としては派手な上下ホワイトのスーツを着ていました。『海を渡る波止場の風』での酒場のシーンでは野村浩次が白のスーツで歌う場面があり恥ずかしい思いをしたことを思い出します。
《上映作品》
- ・4月2日〜8日『南国土佐を後にして』
- ・4月9日〜15日『渡り鳥北へ帰る』
- ・4月16日〜22日『黒い傷あとのブルース』
- ・4月23日〜29日『俺にさわると危ないぜ』
- ・4月30日〜5月6日『東京の暴れん坊』
- ・5月7日〜13日『黒い賭博士・悪魔の左手』
- ・5月14日〜20日『無頼無法の徒 さぶ』
- ・5月21日〜27日『海を渡る波止場の風』
- ・5月28日〜6月3日『やくざ渡り鳥 悪党稼業』
※その他詳細は、過去に制作のページへ。![]() コチラ(別ページが表示されます)
コチラ(別ページが表示されます)